【第41回】初期記憶のミステリー
こんばんは。管理人です。
実は私、今年度から乳児院に関する事業を担当してまして、現在、
それが脳科学、生物学、アタッチメント、発達障害、
と言う理屈を付けて、「バイオサイコソーシャルアプローチ」
まず取り上げるのは「胎児は見ている」で有名なトマス・
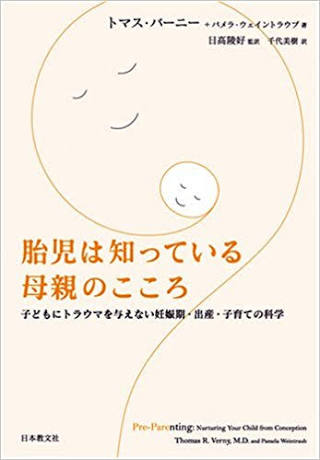
●目次
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
全部の章を一つ一つ取り上げるつもりはありませんが、
ちなみに学術的なところを超要約して3つのトピック(
【1.記憶の起源】
~記憶とは何か。そして、それはいつ始まるのか。
~長いあいだ、人の記憶ーそれまで-
~どこまでさかのぼることが出来るのかは個人差があるが、
~多くの人が、記憶は不思議にも3、
~はじめは卵子と精子が合わさって一つの細胞となり、
~細胞か記憶するなんてどうも信じられないという人は、
~過去の研究から、免疫系の働きは潜在意識レベル(
~ホールはまず、被験者に覚醒した状態でのリラクセーション、
~脳と免疫系は双方向の経路を介して、
~心に蓄積された記憶の反映である情緒が、
~この理論はその後さらに発展した。現在では、体験し、記憶し、
~シュミット(1984)は、"情報物質"という言葉を用いて、
~リガンドが全身に流れるメカニズムは、
~つまり、神経科学の最新の発見からいえば、本当の知性と記憶、
【2.顕在記憶と潜在記憶】
~子どもは、まだ未熟な脳でさえできていない時でも、
~記憶を専門にすると心理学者たちは、
~顕在記憶とは、
~それ以外の記憶が潜在記憶である。
~無意識から意識への移行、つまり、
~こうした記憶が増していくにつれ、胎児は潜在的に、
~事実、多くの研究によって、
【3.出生の記憶】
~子宮にいたころの記憶を自然に思い出すことは稀だが、
~おそらくもっとも説得力があり、記録の数も多いのは、
~では、こうした記憶はなぜ、
~まず一つには、出生前と母乳を与えられているきかんは、
~私たちが出生前と周産期の記憶を失っているのは、
~もう一つの要因は、ストレスホルモンのコルチゾールである。
●コメント
まず「オキシトシン」は別名「愛情ホルモン」
他章で詳しく説明がありますが、
いかに乳幼児期に特定の人との日常的にスキンシップや情緒交流を
まさに「痛いの痛いの飛んでいけ~」が効くのは、
NHKスペシャル「ニッポンの家族が非常事態 第二集 妻が夫にキレる本当のワケ」(2017.06.11放送)
http://www6.nhk.or.jp/special/
しかし、そのオキシトシンが高濃度になると、
忘れられると言うのはある意味幸せ、と言うのもよく分かります。なので、本書では例え未熟児であってもNICU(集中治療室)に入り、母子で相互やり取りする機会が喪失することでの、細胞レベルの記憶や脳の発達への悪影響が生涯に及ぼすリスクについて、とても書かれています。
あと、
~脳と免疫系は双方向の経路を介して、
は体験的に非常に心当たりがあります。実は児相に来てから2~
きっと、脳が「こんなストレス無理、休め!」
つまり、今まさに当時のことを「生物ー心理ー社会」
無意識というと根も葉もない魔術的な怪しい印象も受ける人も正直
【第40回】時間精神医学とBPS
メンバーの皆さま
こんばんは、管理人です。
今回は、本書のメインと言っただけあって、若干長めかと思います。
なるべくギュッとしたつもりですが、そのつもりでお読みください。

理論編
【第1章】心身二元論からBPSモデルへ
【第2章】エンゲルが本当に書き残したこと
【第3章】BPSと時間精神医学
【第4章】 二一世紀のBPSアプローチ
技法編
【第5章】メディカル・ファミリーセラピー
【第6章】メディカル・ナラティヴ・プラクティス
【第7章】BPSSインタビュー
応用編
【第8章】高齢者
【第9章】プライマリケア
【第10章】緩和ケア
【第11章】スピリチュアルペイン
●内容
〜「時間精神医学」とは、1982年にフレデリック・
〜メルゲスの仕事においては、
〜しかも、「時間」という臨床概念が導入されることにより、
〜心理学領域においてなぜ「時間」
「『無意識』体系の事象には時間が無い。
〜しかし、
●コメント【1】
【2】時間精神医学の考え方
本書によると、メルゲスの『時間と内的未来』
①人間は本質的に目標に向かって進む生きものである。
②人は、未来イメージ、行動計画、そして、
③心理的時間の歪みは、その人の未来制御感覚を阻害し、
④時間の歪みの訂正や、未来イメージと行動計画、
そして、
〜ちなみに、西洋社会の直線的時間枠組みでは、
を含めたイメージ図(らせん)はこんな感じです。
▪️心理的時間 ⇨ ▪️未来制御感覚
(シークエンス・ (未来イメージ・
速度・時間志向性) 行動計画・情緒)
⇧
▪️症状 ⇦ ▪️個人的未来の構成
(改善・悪化) (修正・誤構成)
図 、症状の悪循環と症状改善(本書を参考に作成)
〜
〜メルゲスの主張は明解である。精神病、うつ病、
【sequence】連続、順序、連鎖
【第39回】「方法論/認識論」による4つの象限

理論編
【第1章】心身二元論からBPSモデルへ
【第2章】エンゲルが本当に書き残したこと
【第3章】BPSと時間精神医学
【第4章】 二一世紀のBPSアプローチ
技法編
【第5章】メディカル・ファミリーセラピー
【第6章】メディカル・ナラティヴ・プラクティス
【第7章】BPSSインタビュー
応用編
【第8章】高齢者
【第9章】プライマリケア
【第10章】緩和ケア
【第11章】スピリチュアルペイン


【第38回】状況判断能力とコンセプトの融合
メンバーの皆さま
こんにちは。管理人です。
前回は雑談が長引いてしまいましたが、本当はこちらが本題でした。
以前、日本とベルギー、オランダとの文化差について【第13回】日本文化と即興性、育成論
http://lswshizuoka.hatenadiary.jp/entry/2017/07/14/074307で触れましたが、
「社会環境×心理(メンタリティ)」の相互作用を考えるのに、今回もサッカーコラムから
【1】アルゼンチン人から見た日本の特徴
【2】アルゼンチン人監督の育成
について紹介したいと思います。
まず前半はコチラ。
戦術理解は早いが、状況解決能力が低い
エスナイデルが感じた日本の特徴<後編>
https://sports.yahoo.co.jp/m/column/detail/201709170006-spnavi
エスナイデル氏は、アルゼンチン出身のサッカー選手で、スペインのレアルマドリード、アトレチコマドリード等でプレーした後、スペインで指導者のキャリアを積み、2016年11月からJ2ジェフユナイテッド市原・千葉の監督をしている人物です。
●インタビューより
【サッカーでは、時に選手自身が決断する必要がある】
――シーズン始動初期の選手の戦術レベルはいかがでしたか? あなたの戦術に素早くフィットできましたか?
はい、日本の選手は本当に理解するスピードが早いと感じました。監督の指示をよく聞きますし、基本的には従順な選手が多いです。監督としてそういうパーソナリティーを持った選手が多いことは喜ばしいことなのですが、サッカー的には悪いこともあります。サッカーというスポーツにおいては、時に選手自身がイニシアチブを握ってプレーを決断していく必要があります。戦術というのはある一定のラインまでは有効ですが、サッカーで大切なことは相手が何をしてくるかであり、相手に合わせて柔軟にプレーを変えていくことです。
いくら事前に戦術を準備し、相手のプレーを分析していても、いざプレーした時には相手が予想と異なるプレーをしてくることがあります。そうした時に、選手は監督が試合前に指示した戦術を忘れ、状況を解決するプレーを選択しなければいけません。その点に関して言うと、私の選手もまだ苦労しています。とはいえ、戦術面については理解が早いですし、何も問題はないと思います。議論すべきテーマは、監督が話したこと以外の状況が発生した時に解決する手段を持つことです。
――従順な日本人選手を指導することは欧州、特にスペイン人を指導するよりも簡単なことですか?
考え方によりますね。ある一定のことに関して言うと、そうかもしれません。日本で指導する方がやりやすい面はあるでしょう。ただ、私がプレーをしたスペインやアルゼンチン、イタリアといった国では選手自身の状況解決能力が高く、それは日本人選手に足りないところですので、その面では物足りない部分もあります。
――日本人選手の状況解決能力の低さは育成年代における戦術指導不足によるものだとお考えですか?
戦術ではなく教育の問題です。日常生活からも感じますが、日本人はとても模範的で教育された民族です。そうした国で生活することはとても心地良いもので、私は日本という国をとても気に入っています。私自身も日本人に近い性格を持っていますし、ルールや規則を遵守する社会は素晴らしいと考えています。
ただし、サッカーはそうではありません。ルールはありますが、オーガナイズされていないカオスな状況が多々発生するスポーツです。時に選手というのはイマジネーションを発揮しなければいけませんし、自分1人の力で困難な状況を解決しなければいけません。ですので、日本人がサッカーに適応するのは簡単なことではないと思います。
【コンセプトの融合で、日本サッカーは発展する】
――ということは、日本の社会から欧州で通用するコンペティティブな選手を輩出することは難しいことなのでしょうか?
近年、海外でプレーする日本人選手が増加しているので、その点については彼らが大いに貢献してくれるでしょう。海外に行って異なるコンセプトのサッカーに出会った時、日本人選手は素早くそれを理解し、習得します。そうした選手たちが代表で他の選手に異なるコンセプトを伝え、さまざまなコンセプトが融合することで日本のサッカーは発展していく。それはとても重要なことです。
――できる限り若い年齢で海外挑戦した方がいいという考えはお持ちですか?
確かにそうなのですが、一方で日本で成長するチャンスを捨てて無謀に海外へ行く必要はないと思います。世界のサッカーを見渡した時に、強国というのは必ず多くの選手が海外でプレーし、異なるコンセプトを持ち帰り、内外のコンセプトを融合させています。
今、日本代表でプレーする選手の多くが海外でプレーしていることは、日本のサッカーにとってとても重要なことです。その国のサッカーを成長させていくためには外に出ていって学び、異なるコンセプトを持ち帰ってくる選手が必要ですし、同時にそうしたコンセプトを持ち込むことのできる優秀な外国人選手も必要です。
●コメント
サッカーは、ストリート的カオス、チームプレーと個の対応の相互性、求められる柔軟性と困難状況の解決等々、児童福祉現場と共通点が多くて参考になるので、ついついサッカーコラムを多用してしまいます。
しかしながら、役所で勤める身として感じるのは、ホント日本の伝統的な社会組織の多くは上下伝達、指揮命令系統を重んじる「野球型組織」だなぁ、と。
(参考)サッカー型組織と野球型組織
https://jinjibu.jp/smp/keyword/index.php?act=detl&id=598
ちょっと古いですが所謂「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ!」(踊る大捜査線the movie、1998より)に象徴されるような、判断は現場ではなく上司が行うし、その責任も上司が取る組織です。ある意味、部下は守られていますが、余計ことはせず言われた通りのことをこなすだけ。
「戦術理解は早いが、状況判断能力が低い」
なるほどな、と。これまでの日本文化や教育が、規律をきちんと守って言われたことを守れる大人になることを求めてきたし、未だに日本社会では他と違いを生み出すような結果を残すより、規律を守ったり上司に気に入られる方が評価されやすいという現実はあると思います。
エスナイデル氏も言うように、僕も日本は安全で規律が守られて、文化的にも素晴らしいものがたくさんある国だと思っています。ただ「サッカーには合わない」というだけのことです。
時々思うのですが、ストリートチルドレンもいないし、問題を先延ばししても周りが何とか助けてくれるし、それでも別に食べていける社会システムが日本は構築されているよな、と。
すると、社会システム信者といいますか「安全安心の手段としてのシステム」だったはずが、いつの間にか「システムから外れたり、システム自体が壊れることへの恐怖」にすり替わっているのか、そもそもシステムが機能して目的を果たしているのかは思考停止で、「決まりだから」とシステムを守ることに頑なに縛られている人に出会うことが時々あります。
なんとなく最近、日本世間一般の「失敗」という言葉に対する過剰なアレルギー反応ようなものを感じます。それは文化的に、輪を乱すと周りから忌避されやすい環境、「出る杭は打たれる」くらいならリスクを取ることを避ける「社会環境×メンタリティー」の相互作用の積み重ねがあるのかもしれませんが、それだけかなぁ、と。
TV番組のコンプライアンスに象徴されるように、感覚的に80~90年代はもう少し失敗に対する許容度があった気がするんですよね。やっぱりバブル以降ですかね。世の中全体の将来に対する悲壮感というか悲観的な雰囲気。
【第35回】コラムで、
~思春期以前は「安全のために保護する時期」、思春期以降は「失敗を担保する時期」
という紹介をしましたが、大人が不安だから子どもにチャレンジさせない→必要な経験が教育・育成段階で足りない→成功体験もなく不確実性に耐えられないので次の世代にもチャレンジさせない
という悪循環ループに突入していないかな、と。
ただ社会状況を変えられるわけではないので、状況を打破するためにどうするかと言うと、やはりエスナイデル氏も全く異なるコンセプトを融合するという「異文化交流」的な事を言っていますね。
では、エスナイデル氏が言う「私がプレーをしたスペインやアルゼンチン、イタリアといった国では選手自身の状況解決能力が高く」とは、どのようにして培われているのか。
また南米一を決めるコパアメリカ2015ではベスト4の国全部がアルゼンチン人監督という事態が起きている程、アルゼンチン人のサッカー監督が評価されているのは何故か。
その一端が垣間見れる記事がありましたので、それがコラム後半です。
シメオネら名将を次々と輩出“アルゼンチンの松下村塾”に潜入
https://www.footballista.jp/interview/38186
~やはり、欧州で選手としての経験を積んだ者が指導者に転身していることが大きな理由の1つでしょう。アルゼンチン人特有の情熱と勝利へのこだわり、自信、説得力とリーダーシップに、欧州のトレーニングメソッドや戦術を取り込むことによって、多彩で優秀な監督が生まれます。それ以外にも、秩序、責任、相手に対する敬意など、欧州に渡った選手でなければ習得できないピッチ内外での基本的な要素が取り入れられていることも大事なポイントです。特にアルゼンチン代表でマルセロ・ビエルサ監督の指導を受けた世代から、欧州式メソッドとの融合が目立つ傾向を感じますね。
~とにかくビエルサの指導法そのものが、従来のアルゼンチンにおける典型的なトレーニングメソッドとは大きく異なります。一昔前までのアルゼンチンでは体力作りとゲーム式練習が基本で、夏季キャンプでも最初の1週間はとにかく走り、その後はとにかく試合に試合を重ねるというやり方でしたが、ビエルサは細かく具体的な戦術練習に力を入れます。代表でビエルサの指導を受けた選手たちは、あのやり方が非常に効果的だったことを身をもって知らされているわけです。でも気をつけてもらいたいのは、ビエルサの指導法をそっくりそのまま真似している者はいないということです。シメオネもポチェッティーノも、それぞれが異なる条件下で独自の判断をもってチームを作っています。いかなる環境に置かれても優れた問題解決能力を発揮するのが、これまたアルゼンチン人の特性なんですよ。
~アルゼンチンは社会的・経済的な問題が絶えない国ですが、そのために国民は無意識のうちに即興で解決策を見出す力を養われていて、その場にあるものを使ってトラブルを克服することに慣れているのです。『さあ困った』と腕を組んで考え込んでいたら、問題は山積みになる一方ですからね。決断も早いですよ。この特性こそ、アルゼンチン人監督が国外でも活躍できる理由と言えるでしょう。
●コメント
やはり、異文化交流。まずアルゼンチンには、状況解決能力が養われやすい不安定な環境があり、そのメンタリティのベースを持った人物が、欧州的な戦術やトレーニング理論を取り入れつつ、さらに自身の解決能力によって独自のメソッドに進化させている、ということですよね。
どちらが良い悪いではなく、Aを持ったものがBを取り入れる、足りなかった視点を補い、多角的視点を融合してるという事かと。じゃあ本家の欧州人監督はアルゼンチン人監督より優れているのかと言えばそうではないんでしょう。
アルゼンチン人の元一流選手にとって「認知ー体験ー感情」の足りない「認知」を補うものが欧州的メソッドであり、監督養成学校で他の生徒が元一流選手と共に学びながら話を聞くことで「体験」を補足する相互作用を生むサッカー監督養成システムをアルゼンチンは作っている、ということみたいですね。
じゃあ、このシステムをそのまま日本に当てはめて上手くいくのかと言うと、そうではないと思います。状況解決能力って「たくましさ」と通じる気がしまして、放任主義というかネグレクトで育った子の中には、良くも悪くも生きてくための「たくましさ」を身につけている子っていますよね。
社会的・経済的状況から真似る必要があるのかと言ったらやはり違うし、日本には日本の文化と歴史の良さがあります。アルゼンチンはアルゼンチンの発展のプロセスがあるし、日本は日本の発展のプロセスがある。それは、組織や個の発展成長にも同じことが言えて、「〇〇だから」という固定概念ではなく、国も組織も家族も個人もそれぞれが時代の影響を受けて変化し、その変化にそれぞれ影響され合う相互作用で考える必要がありますよね。
今のアルゼンチンの監督育成メソッドだって、進化がなければ10年後には時代遅れのものになっている可能性だってあります。その支援対象ごとに今どんな力が必要とされ、これまでの環境(家族、地域)で培われている資質は何で、さらに何を積み上げていく必要があるのか、その人の強みと弱みをきちんと把握しながら、常にオリジナル版の個別支援をアップデートし続けるしか成長進化の道はないんだろうと思います。
始めに言いましたが、サッカーと児童福祉(=社会的養護、集団養育)は似ている点が多いなと思います。今回のサッカー選手や監督を育てる視点は、児童福祉の子どもや支援者の育成を考える上で、そっくりそのまま真似る意味ではなく、異分野の視点を取り入れると言った意味で、とても参考になるなぁ、と思います。
個人的には、日本の児童福祉現場において、ざっくり言うと、80年代後半~90年代前半に「不登校→虐待」問題に焦点が当たり始め、阪神大震災があった辺り90年代半ばから後半以降10年間で「トラウマ・発達障害」が広く認知され始め、さらに2000年代半ば以降のこの10年間「LSW」的ナラティブの再考が起こったという、約10年サイクルで新しい波、パラダイムシフトが起こっているんじゃないかと思っています。
そして、これらが時代遅れになる訳でなくて、認識されてから、どう実践に繋げるのかで10年、どうシステム化するのかで10年、という積み上げのバージョンアップが必要なんだろう、と。
「平成」もいつまで続くかわかりませんが、来年度以降、平成30年代の今後10年は、最近の児童福祉司の研修整備、公認心理師の国家資格化、法改正による司法関与や学齢期前の里親委託推進の流れ等々、日本の児童福祉にとって変革の10年になりそうな予感がします。
なんか話が大きくなっちゃいましたが、常に揺れながら変化していく時代の波に、LSWが何とどう融合し、どういう発展を遂げていくのか興味深いですし、僕もいち実践者として色んな分野とアイデアを取り入れながら考えていきたいなぁ、と思います。
ではでは。
【第37回】ラブライブと情緒的発達
こんばんわ。管理人です。
突然ですが「ラブライブ!サンシャイン‼︎」というアニメを皆さんご存知ですか?
最近、やたら東大生が出るTV番組が多いですが、昨夜たまたま観ていた「さんまの東大方式」という番組内で、ある東大生が会いたい有名人がこのアニメの声優さんだったんです。
まぁ、よくある萌え系アニメかと思っていたら、妻に「え!知らないの⁉︎」信じられないくらい勢いで驚かれまして。
どうやら静岡県沼津市(東部地区、伊豆の北側)に実在する中学校を舞台に、その在校生がアイドルになっていくというストーリーで、沼津市はまさに「ラブライブ」フィーバーなんですって。
ラブライブの画が描かれた市内バス目当てに、カメラを持ったオタク達が沼津駅前に列を作り、夏休みには舞台になっている中学校の校内にファンが侵入する事態になっているんだそうです、沼津市で働いていた妻によると。
よくよく調べたらラブライブ声優ユニットは紅白歌合戦にも出てるみたいで、これは全国規模の人気だろうし、もれなく発達障害系でハマっていく沼津男子が続出らしいです、妻によると。
でも、同じ県内の浜松市(西部地区、愛知県の隣)で僕が児相で関わる子ども達からラブライブの「ラ」の字も聞いたことなくて、オカシイなぁ、でも150kmも離れてるし地域差ってやつかなあ、なんて思ってたんです。
すると、ある東大生が興味深い事言ってまして「思春期が3年遅れてきて、中学生の時は周りがアイドルの話しとかしてても何で興味があるのか全然わからなかったけど、受験勉強の時にやってきて大変だった」と。
また、別の色白の物静かな東大生が会いたい有名人が芸人を「くまだまさし」と言うので、みんな何で?と聞くと彼は、こう答えるのです。「くまだまさしさんは、自分の数少ない感情が動く瞬間を与えてくれる人です」「しょうもない芸を見ていると、身体の中が熱くなって楽しい幸せな気持ちになれる」と。
そうそう、これこそ虐待がない純粋な発達凸凹や感覚凸凹形成の感受性アンバランスによって、アタッチメントや情緒的発達が遅れて育つやつですよね。さすが東大生!ケースの子とは言語能力が違うな、なんて気軽に観てましたけど、これってかなり貴重な語りだなと。
番組コーナー的には、頭が良すぎて他人になかなか価値観や恋愛観をわかってもらえないことを、さんまさんが面白おかしくイジって笑いに変えてるわけですが、見るからに周囲と感覚が違いすぎて生きにくい、他人の感情が読みにくい、全員ではないですが番組的に面白おかしくなってるのは明らかに発達障害系の人たち。
そこにネグレクトや虐待による感情麻痺が上乗せされるわけですら、そりゃ、思春期段階では精神年齢が低すぎて「ラブライブ」=異性への興味まで追いつかないのかもな、と。
一昔前はそうばかりでもなかった気がするのですが、年々、児相で関わる子たちの精神年齢が幼くなってきているような印象を僕は持っていますし、約10年前から一緒にやっているケースワーカーもそう言っていました。
ちなみに、妻のフィールドは病院や巡回相談なので、つまり在宅ケース。同じ発達凸凹の課題を抱えていても、在宅児と施設入所児ではなんかアベレージが違うよな、と思ったりするわけです。
前段の雑談のつもりが長くなってしまったので、これで1つのコラムにします。
ちなみに散々、発達凸凹って言ってますが、このコラム書くのに没頭しすぎちゃって、気がついたら降りる駅を乗り過ごしちゃった僕も全然人のこと言えませんね。
ではでは。
【第36回】DSMやエビデンスへの固着

理論編
【第1章】心身二元論からBPSモデルへ
【第2章】エンゲルが本当に書き残したこと
【第3章】BPSと時間精神医学
【第4章】 二一世紀のBPSアプローチ
技法編
【第5章】メディカル・ファミリーセラピー
【第6章】メディカル・ナラティヴ・プラクティス
【第7章】BPSSインタビュー
応用編
【第8章】高齢者
【第9章】プライマリケア
【第10章】緩和ケア
【第11章】スピリチュアルペイン
【第35回】バイオサイコソーシャルアプローチ

はじめに
理論編
【第1章】心身二元論からBPSモデルへ
【第2章】エンゲルが本当に書き残したこと
【第3章】BPSと時間精神医学
【第4章】 二一世紀のBPSアプローチ
技法編
【第5章】メディカル・ファミリーセラピー
【第6章】メディカル・ナラティヴ・プラクティス
【第7章】BPSSインタビュー
応用編
【第8章】高齢者
【第9章】プライマリケア
【第10章】緩和ケア
【第11章】スピリチュアルペイン
おわりに
●内容
~今や、「生物心理社会モデル」という言葉は、医療・
~このモデルの臨床場面における使用の誤りが指摘されている。
~二つ目は、このモデルを「全人的医療」
~そこで、私たちは「BPSアプローチ」と呼ぶ。臨床はモデル(
~BPSアプローチとは、
●コメント
