【第47回】漢方医が語る西洋医学と東洋医学
メンバーの皆さま
おつかれさまです。管理人です。
昼間は暖かい日が続いていますね。予定帳を見ると「もう今年も終わっちゃうな…」なんてしみじみした気分にもなりますが、つかの間の「過ごしやすい秋」を味わいたいですね。
前回、西洋東洋の文化差やマインドフルネスなんて話題に触れたら、ちょうど関連するような記事( 『命の繋がりを自覚して生きる』致知2017.11月号) を見たので、今回はそこから。
■健康の本質を見ていない医者
~病気や死が怖かったんですが、私の場合は、
~ところが、これまで長生きできると思っていたのに、
~理由はいろいろありますが、
~毎年忘年会シーズンになると、「食べる前に飲む!」
~これに対して東洋医学は「体に悪いから、暴飲暴食はするな」
~けれども西洋医学は、傷を覆ったり、
■文字にできない技能をいかに習得するか
~外科と漢方というのは、実はよく似ているんですよ。
~言語化できる客観的な知識のことを「客観知」といい、
~漢方には「証」というものがあります。
■自分の体の声をよく聴くこと
~まずご理解いただきたいのが、
~その上で大事なことは、
~体というのは、
~漢方の何がいいかというと、
●コメント
僕の知り合いで「飲み会前にウコン飲むと調子良くなって呑みすぎちゃうから」と言ってウコンの力を飲まない人がいます。「ウコン飲んでるし大丈夫かぁ」と限界以上に呑んじゃうことに歯止めをかけてるそうです。確かに、身体のためにウコンを飲むなら、そもそも暴飲しないのがいいわけです。その人は それで結構なハイペースで呑みますけど(笑)
〜薬があるから病気になってもいいという発想が西洋医学のベースにはあるんです。
は極端な表現かもしれませんが、桜井氏が言う「健康の本質を見ていない」とは、おそらく「木を見て森を見ず」の状態。西洋医学は局部としての「病気」は見ているが、身体全体や生活全体のつながりとしての「健康」を見ていない、ということかなと。
僕の中では、西洋医学はキュア(cure)、東洋医学はヒール(heal)のイメージ。 どちらも万能というわけではなく、状態に合わせてより効果的な方を選択したり併用すればいいんだと思います。
木(部分)を見るのか森(全体)を見るか、何を撮りたいかの構図によってカメラズームが変わるように、状態に合わせて何に焦点を当ててアプローチするのがいいのか、両方検討しながらベストな形を探して行くことが大切なんだろうと思います。
※参照:【第18回】「cure」と「care」の違い
また、第18回コラムで【heal】の語源が、ギリシャ語の【holos】「完全な姿(本来のあるべき姿に戻る)」で、healに状態を表すthを付けて【health】「健康」であることに触れましたが、東洋医学の考え方は、人間がもともと持っている治癒能力を活かしたり高めたりする【heal】のイメージが僕の中にはあります。
きっと東洋的に言う「気の流れ」って、人が本来あるべき状態かどうか、本来持っている維持機能が正常に動いているかどうかの「流れ」を指して言っているのではないかと思うんです。僕は気功師ではないので推測ですが、あくまで。
僕自身、数年前までは、漢方とか気功って根拠はないし、気の持ちようじゃないかなぁ、なんて懐疑的な思いが正直ありました。しかし、これって、一般の多くの人の感覚なのではないかと思います。
ところが、気功の施術によってホルモンバランスが整えられたり、ドーパミン分泌や脳の部位の活性化が確認されているみたいですから、まさに「気のおかげ」で生理学的な変化が起こっている説明は付くようです。
また言葉を替えれば「気の流れが悪い」「邪気がある」というのは、おそらく生理学的にはホルモンバランスの崩れや機能不全を「気」で 察知して言っているんだろうなと思います。
じゃあ、それをどう察知するのかという話になるわけですが、それは言葉にできない「暗黙知」であり、感覚感性的なものということになると。
処方箋にあたる漢方の「証」も「その時の体の状態のパターンや、特定の漢方薬が効く状態のパターンのことですが、客観的なデータで判別されるものではなく、言語化できない雰囲気や何となくの感じが大事にされるんです」
と言うように、ブルース・リーの「Don't think. Feel」の世界ということ。
しかし、これは東洋医学に限った話じゃなくて、外科医の世界でも、音楽や料理でも同じことが言えます。同じレシピや楽譜があったとしても、 「腕」や「道具」の違いで、味や音色は全く違うし、全体の仕上がりは他の人が簡単に真似ができるものではない「暗黙知」ですよね。そして、芸術や表現の世界では、 独特な感性が希少価値として重宝されることも珍しいことではありません。
ただ【第42回】コラムで、
〜母親の影響を受けにくいセロトニン・トランスポーターの長いタイプの多型を持つ子どもは、 白人は6割だが、アジア人種は1/3にとどまる
とあったように、集団の感度の違いによって、より良い伝え方に、歴史文化的な変遷があった結果の違いなのかもしれないなと思うんです。
誤解をおそれず単純化すると、おそらく欧米人の多くは「頭で理解→実践→感覚感性を磨く」の順がわかりやすいし、日常生活もそういう思考で動いているし、そのような説明を作るのも得意。
一方で、多くの東洋人は感性が高く、良くも悪くも周囲に影響されやすいので、「雰囲気で感じ取る→実践→感覚的に経験を体系化して整理する」方が自然で日常的だし、「身に付く」とか「腑に落ちる」とか身体を使った言い回しが多いのは決して偶然ではなく、伝統的に学ぶとはそういうもんだと思っているので「なんとなく」「普通わかるでしょ」で済ませちゃう、
そんな傾向がある気がします。なので、ハッキリ言って言語化理論化という部分では西洋文化は優れていると思います。しかし、自分や相手の機微や雰囲気を察する感覚的なものは、東洋文化の人の方が平均的に高いと思うんです。
どちらが優れている劣っているではなく、人の能力に凸凹があるのと同じように、文化的な集団的な得意不得意はあるので、得意を伸ばし不得意をどう補うか。特性に合わせた成長・子育て支援のニーズは、個も集団も本質は変わらないよな、と思います。
~体というのは、病気になる前に必ず何らかのサインを発しているはずですから、自分の体の声をよく聴くことが大切です。
~漢方の何がいいかというと、自分の体の変化を感じる訓練になるんです。
これって、子育ても対人支援も感じるものが「相手」になっただけで似ているよなと思います。
基本的には子どもやクライエントが発信したニーズをキャッチし適切なタイミングで応答できるか。 そして、その中には何か具合が悪くなりそうなサインも含まれているわけで、そこを的確にキャッチして大事に至る前に早めの対処ができるかどうか。サインを見逃し放っておいて、激痛が走ってから慌てて手術するのは本来のあるべき支援やお世話の順番ではないと思います。
それでも事情があってやむなく悪化してしまった部分へのピンポイントのアプローチは「西洋医学」の得意分野、本来の健康的な心身の状態に近づける全体的なアプローチは「東洋医学」の得意分野。
視野の広いお医者さんは、この西洋東洋の特質や得意分野を踏まえた上で、西洋薬と漢方薬を併用してアプローチしてくれますよね。
【参考】健康Saiad「西洋薬と漢方薬の違い」
対人援助でも似たような整理やコンビネーションが必要だと思うんです。今の自分が担っている役割やアプローチは局部なのか大局なのか、応急処置なのか継続支援なのかをわかっていること。そして、一人で全部は担いきれないので、片方は信頼して任せることで自分は別の役割に専念できるように、チームで意思統一して役割を分担していく。それが「連携」ですよね。
ごちゃごちゃ書きましたが、LSWの発想って漢方や東洋医学に近いのかな、と最近思うんです。部分じゃなくて全体的な視点。抗生物質みたいな即効性じゃなくて漢方薬みたいにじわじわ効いて、本来持っている力を引き出すみたいな。
そしてLSWでは「時間志向」が、東洋医学でいう「気」に近いイメージかなと僕は思っています。時間志向とは「過去ー現在ー未来」のどこを考えているかということ。そのグルグル考える流れというか、頭や意識の中で過去や未来を行ったり来たりするスムーズさを、本来あるべき状態に整えたり整理するのがLSWの僕のイメージです。
なんですけど、「ライフストーリーワーク」と言う横文字の表記が西洋医学的な治療をイメージさせる誤解が起こりやすいなぁと思います。頭の中で、支援=西洋的「治療」に凝り固まっていると、即効性がないと支援に意味がなかったんではないかと不安になる人も実際には多いことは、現場で話をしていてすごく感じます。
ただ、「時間精神医学」には、時間志向の焦点化が偏っている人がどのような状態になるか、また精神障害が起こると時間感覚はどうなるか、どのように支援するか感じ取るヒントが散りばめられているな、と思って未整理のまま紹介だけしました。
(詳細は【コラム】「バイオサイコソーシャルアプローチ」を参照ください)
ある意味、まごのてblogは「暗黙知」の言語化に無謀ながら挑戦して試行錯誤しているみたいなところがあります。なので話題があっちこっち行ってしまうのはお許しください。
そういう他人の混沌としてあやふやな、あーでもないこーでもないと考えるプロセスを共有いただいて、メンバーや読者の皆さまの思考や内省を深めるお手伝いに少しでもなれば幸いです。
ではでは。
【第46回】愛着形成とオキシトシン
メンバーの皆さま
こんばんは。管理人です。
はやくも11月ですね。だいぶ朝晩は冷えてきたので、
少しでも過ごしやすい秋が続いて欲しいものです。
で、今回「胎児は知っている母親のこころ」の『第7章「親密さ」
一応、後付けで3つのトピック(アタッチメントの生物学/
●コラム
愛着(アタッチメント)とは、
「愛着」は、愛着理論の専門用法を指しているので、
(※愛着の一般的用法と専門用法の違いは【第29回】
■アタッチメントの生物学
アタッチメントという現象の特異な点は、
アタッチメントには、
オキシトシンの不思議な性質は、その相互的な関係性で、
ちなみに、下記の記事『オキシトシン分泌を増やす方法とは!? 専門医師が解説! vol.2』等によると、
性行為やエステなどの触れ合いでもオキシトシン分泌は起こると。
ただ、
また、
これは従来「情動調律」と呼ばれて説明されている、
【参考】『情動調律〜感情の調整力や安定性はどこから発達する?
また、オキシトシンには、痛みや辛さを和らげる作用もあるので、
また愛着が生理学的現象であるということもあって、
ちなみに、このオキシトシン・システムが弱いと、
と考えると、「痛いの痛いの飛んでけー」
赤ちゃんを見ると「かわいい〜」
従来のアタッチメント理論は「心理ー社会」的側面で、
ちなみに、最近の生物学的な研究では、オキシトシンが動物の「
【参考】
さらにアタッチメントから脱線しますが、自閉症スペクトラムの社
【参考】
これらから思うことは、情動調律でも同調でも、
■社会文化的な適応とオキシトシン
若者の恋愛離れをオキシトシンで説明していますが、
当たり前ですが、社会的な情勢(環境)によって、
動物でも似たようなことが起こるようで、閉じた柵に犬とヤギを入
おそらく野生動物は、
なるほど以前に【第42回】コラムで、
が、動物だけでなく人間にも似たことが言えて、多数派が「
例えば、伝統的な子育ても、日本人は密着型で境界が曖昧、
どこかの新聞の投稿記事で、
現在では、欧米でも「インファント・マッサージ」
マインドフルネスの流行りにも感じますが、
なので、西洋東洋、南米北米、
■過去の語りとオキシトシン
最後に、LSWに直接関係しそうなオキシトシン話としては、英国
他も含めて論文を直接みていないので想像にはなりますが、
現在の状態が荒れた状況でLSWをしても、「
もちろん、愛着(アタッチメント)がオキシトシン・
やはり近接領域の他分野の話は面白いですね。
ではでは。
【第45回】新生児の感覚と神経はこうして発達する
メンバーの皆さま
こんにちは。管理人です。
どうやら、また週末に大型台風が到来ですね。
前回の台風では、月曜の朝、普段通勤で使っている東海道線が完全ストップしてしまったので、やむなく新幹線で通勤しました。
仕方なく、新幹線が乗れる駅まで30分ほど歩いたのですが、乗り遅れそうだったので、GoogleMap片手に近道を急いでいたらiPhoneがスルリ。
画面はバリバリ、開いた画面は勝手に動き出す始末。そして、新幹線も遅れているので遅刻を連絡しようにも携帯は使えず。
挙句に初めて新幹線の公衆電話を使ったのですが、なんとテレフォンカード専用で、この時代に電話機の横の販売機で1000円テレカを購入して電話すると言うレアな体験をしました。
結局、携帯は買い替えだったのですが、ドコモの保証+ポイントで5000円程で新品と交換できました。携帯も使用3年で電池もすぐ無くなったちゃう状態だったので、結果オーライです。
ただ、携帯が無くなるとホント焦りますね。まぁ、結果的に元より携帯の状態が向上して、さらに面白い貴重な体験もできたと言うストーリーになったから、今回は良かったです。
しかし、当たり前にあったものを突如として失う「喪失体験」が引き起こす将来の不安、それが元通りになるかならないか分からないことの心配、そして、どうにもならないと知った時のショックと言ったら計り知れないですよね。
はぁ、その日のうちにdocomoショップ行けて良かった良かった。早期介入、早期支援の大事さが身にしみました。
以上、プチ喪失体験とナラティブによるセルフケア体験でした。皆さま、今回の台風もお気をつけください。
では、コラムです。

●目次
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
今回は「第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する」を中心に、新生児の脳の発達について。
~新生児に対する小児科医たちの誤解は、かなり昔に始まっている
~1970年代に入ってようやく、…心拍を記録する電極、おしゃ
~赤ちゃんはもちろん、最初から親の気分や調子を合わせている。
■新生児の感覚
【出生時~1週間】
・出生の数分後、分娩室で、明暗はっきりした部分のある物体、た
・生まれたばかりの新生児は、大人の顔をじっと見つめ、大人の発
・見つめていた物体がゆっくりと動くと、数分間はそれを目と頭で
・三次元的な感覚をもち、ある程度目と手を協調させて動く。
・自分の母親とほかの子どもの母親を、母乳のにおいや腋(わき)
・食べ物に関連した香りのうち、ミルクのような香りや果物のよう
【1週間~】
・生後一週間までに、母親の声をほかの女性の声と区別できるよう
・生後数週間で、父親に対して、母親に対するのと全く違う態度を
【2か月~】
・生後八週間で、物のかたちや色の違いがわかるようになる(たい
・赤ちゃんは、無意識にものをしっかりとつかむ力をもって生まれ
たいていこの強靱な握力は失われるが、かわりに別の能力が見られ
【4か月~】
・生後四ヶ月で、生き物とそうでないものとの動きを区別できるよ
【5か月~】
・生後五ヶ月で、唇の動きが言葉に対応していることに気づく。
・目と手の協調運動ができるようになるためには、当然ながら、そ
【6か月~】
・生後六ヶ月になると目の焦点がしっかりと定まる。
~ピアジェは能力の習得を段階ごとにわけたが、今日の神経科学者
~PETスキャン(陽電子放射断層撮影)からは、脳の特定部分が
~ここで注目すべき点がいくつかある。健康な乳児の脳の各部位は
~辺縁系が活性化しているときは、子どもは情緒のコントロールを
~視覚などの感覚に関する研究によれば、出生後に活性化する部位
●コメント

すると、
と読んだ時に「あれ脳幹は?」とふと思いました。そうです、少し前のコラムをよく思い出してみてください。
~胎児の脳は、アドレナリンやコルチゾールなどのストレスホルモンに長い間さらされると、不必要な時に、「戦うか逃げるか」の反応を起こす習慣がつきやすい。しかも、この習慣は生涯続く。
~ストレスの高い母親の胎児は、心拍数が著しく増加し、その後正常に戻るまでの時間にかなり時間がかかった。ここでいうストレスの早い母親とは、血液検査で高濃度のストレスホルモンが認められ、不安が強くまわりから協力があまり得られないと質問票に回答した母親である。 いっぽう、望んだ妊娠をして、適度な自尊心があり、周囲の協力にも恵まれた母親の胎児は、穏やかで、心拍数が正常に戻るのが早かった。
(【第43回】子宮内の胎児の意識と発達
ハッキリとは書かれていませんが、これらの記述から、おそらく哺乳類以前のもっと生物的な[カエル脳]=脳幹あたりの部位がもっとも活性化する臨界期は、胎児期であると読み取ることが出来ます。
そして、情緒コントロールを司る大脳辺縁系がもっとも活発になるのが新生児期で、生後二ヶ月と三ヶ月ではすでに、視力と感覚運動能力が発達する視 覚皮質と小脳半球の代謝に移ってしまうというのは、初めて読んだ時は衝撃でした。
「情緒・感情のコントロール」の課題って、虐待で関わる子のほとんどに当てはまってしまうわけで、支援者はそれをどうしようと散々悩まされるわけですが、一番効果的な関わりの時期は、すでに胎児期~生後1ヶ月程で終わっていると。
それは率直にいうと、もちろん過去は変えられないんですが、多くの子が抱える「感覚や感情のコントロール」課題とその支援に伴う大変さについての悩みは、ほんの胎児~新生児期の数ヶ月間の支援があれば、こんなに苦労することはなかったのではないか、という想いです。
それほど胎児期~新生児期の養育の影響は、その後のその子の人生に大きな影響を及ぼすということですし、それに一番苦しむのは誰でもない本人に違いありません。しかも自分ではどうにも出来ないことで。
これらの仕組みを知らされずに「早期支援!予防的関わり!」と言われても、支援者はただ急かされているようにしか思えませんが、きちんと説明され今やっていることの意義や意味付けがされて、ようやく母子保健や母親支援(家族の協力を含め)の質が変わるんだろうな、と。
前々回に「ポピュレーションアプローチ」の話にも触れましたが、虐待相談件数がうなぎ登りとか、発達障害を早期発見しましたとかでない文脈。もちろん、事が起こってからの対応も必要ですが、「虐待が脳に影響を与える」という事後のネガティブ文脈だけじゃなくて、 同時に「早期支援・出産前後のママ支援は、子どもの脳の発達を支える」という事前のポジティブ文脈ももっと声を大きくして言われて欲しいな、と思います。
最後にLSWに絡めて言うと、LSWの一般イメージは、施設入所児童が「私のお母さん、どうしてるの?」と言ったり、現れが出てようやく過去を扱おうとするような事後対処に注目が集まりがちと思います(このタイミングでしか扱えないケースもありますが)。
でも、大事なことは、まずその時に起こった喪失体験(離別、転居など)にその場その場でできる限りの対応ケアされているか。児相が関われる場面で言うと、やむなく家から離れて一時保護や施設入所する時に、きちんと理由が説明されたり、それに伴う本人の想いや感情をきちんと聞いたり表現する場を与えているか。
そして、入所後もその状況理解や言い残した未完の感情がないか確認したり、知り得る家族の状況を伝えたり。リアルタイムでされるべき喪失体験へのケア(扱うべき本人の想い)を積み残すことで、後々に必要な支援は実はどんどん増えていってしまいます。
もちろん、どんなに気をかけても本人の状態から扱いきれない想いや喪失体験はあります。ただ、支援対象を個ではなく全体として見たら、今ここで出来る早期支援やケアをないがしろにして、事後対応にばかり囚われるのは明らかに順番が違うし本末転倒というのは、子どもの脳の発育の支援もLSWも変わらないなぁ、と思います。
あと今回は、落とした後のdocomoサポートに救われましたが、僕がやるべき順番は、落としても守ってくれそうな携帯カバーの検討ですね。
ではでは。
【第44回】水戸と「ひよっこ」とLSW
メンバーの皆さま
こんにちは。管理人です。
先ほど「LSW全国交流会@水戸」が終わりまして、ただ今、
全国交流会は今年も興味深い内容でしたが、
『ひよっこ』医療監修者に聞く、
我が家では、妻(と息子:
妻から時々「〇〇ちゃんと△△さんがいい感じになって来た」
父の記憶喪失って、主人公みね子にとっては、
〜糸川 人間の記憶には4種類ありまして、
――記憶を失っているはずなのに、
糸川 記憶はどこかで保たれているはずなんです。
――記憶を失っているはずなのに、
糸川 記憶はどこかで保たれているはずなんです。
この話は日常的な生活支援の大切さを、
でも一方で、記憶はどこかで保たれていて、田植えのような「
この辺りは、
記事の続きを紹介をすると、
――「悲しい出来事に、幸せな出会いが勝ったんだよ」
糸川 僕の専門である精神医学の世界では、疾患の原因になる出来事が「
糸川 僕の専門である精神医学の世界では、疾患の原因になる出来事が「
と語られています。
今年の交流会は、いろんな方々の話を聞いたり、
ちなみに、昨夜の夜中1時頃にラーメン、焼きチャーシュー、ライスの暴食したにも関わらず、お腹具合は行きと違い穏やかに帰れました。美味しかったし、良かった良かった。
ではでは。
【第43回】子宮内の胎児の意識と発達
メンバーの皆さま
こんにちは。管理人です。
現在、今日明日に行われる「LSW全国交流会@水戸」
ちょっと節約して、沼津→
まぁ沼津からなら座れるし、
コラム書きで気を紛らわせて、
東京、寒いです。茨城はどうなのでしょうか。
では、コラムです。

●目次
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
今回は、胎児期にかかわる第2、3、4章をまとめて。
~数々の研究によれば、
とありますが、トピックを4つ(胎児の感覚/痛みと回復力/
■胎児の感覚
以下は、胎児の発達について、本書を整理して抜粋したものです。
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
今回は、胎児期にかかわる第2、3、4章をまとめて。
~数々の研究によれば、
とありますが、トピックを4つ(胎児の感覚/痛みと回復力/
■胎児の感覚
以下は、胎児の発達について、本書を整理して抜粋したものです。
【1ヶ月】
・妊娠二十八日前後で胎芽は六ミリ程度になり、
【1ヶ月半~】
・六週前後でおよそ十二ミリになると、
・早くも七週目に触覚があることが報告されている。
・
【4ヶ月~】
・四ヶ月目までには周囲の世界を探索する能力が飛躍的に発達し、
・十七週目には皮膚の大部分に感覚が生じる。
・嫌な味のする物質を子宮内に注入すると、
【5ヶ月~】
・五ヶ月目には、大きな音に対し、
・人間の聴覚機能は、二十週目には大人と同程度になる。
・十九週目から二十週目に初期の脳波が現れ、
・胎児には、学ぶのに必要な脳の構造そして意識さえもが、
【7ヶ月~】
・二十七週目には、母親の声にとくに敏感になる。
・二十八週目ごろには違う音色を聞き分けられるようになる。
・胎内で聞いた言葉は、特定のしゃべり方や方言のもとになる。
【新生児】
・人間の脳は子宮にいるときからすでに言語を学びはじめている。
・研究者によれば、出生直後の新生児は、
~その詳細についてはまだ推測の域を出ないが、
~胎児が成長するにつれ、
■痛みと回復力
~痛みの経路は、かなり早い時期に作られる。
~早生児も痛みに対して明らかな反応を示す。
~実際、解剖学的に見れば、
~
~というのも、
~胎児の脳は、
~いっぽう母親がつねに喜びや愛を感じていると、胎児の脳は"
~パシック・ワダワは、母親のストレスの影響を測定するために、
~その結果、ストレスの高い母親の胎児は、
~いっぽう、望んだ妊娠をして、適度な自尊心があり、
■母親のストレスとうつ
~母親の過度のストレスは、子供の学習能力にも影響する。
~頷けるのは、
~その結果、影響を受けやすい子どもの場合、
~妊娠中のストレスが深刻な影響をもたらすのであるなら、
~同研究班は、
~研究者によれば、妊娠中のうつは産後も続くことが多い。
~
■胎児のパワーを高める
~神経科学の最新の発見によれば、
~マリアン・ダイアモンド(有名な神経科学者)
「
~胎児の脳細胞は栄養素が足りなかったり、
~「全細胞数の50~65%もの大量のニューロン消失が、
したがって、初期のニューロン機能にかかわりのないものは『
神経細胞のを健全な状態にしておくために、
~「神経系というものには、可塑性に『朝』があるばかりでなく、
●コメント
すごくざっくり言うと、
みたいな感じでしょうか。
もちろん小難しいことが苦手な方には、
児相に配属された当初、「
つまり妊娠期に夫婦不和や離婚、
したがって、同じような過酷な状況下でも、
この辺りが早期支援、予防的関わりの根拠になるのでしょうが、
そこにあった説明は、従来のハイリスクアプローチは、
そういう意味では、
LSWに限らず、子どもの育ちに関する胎児期~
ということで、次回は新生児期について触れて行きます。
ではでは。
【第42回】胎児期のバイオサイコソーシャル
メンバーの皆さま
こんばんは。管理人です。
臨床心理士の方はわかると思うのですが、ここ数日、
あの受験資格の案内を正確に解読できている方って、
結局のところ講習会(7万円+テキスト代別)
新しい環境の変化に適応するのって、やっぱり大変です。
心理士でない方にはよくわからない話でスミマセン。
では、コラムです。

●目次
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
今回は「はじめに」と「第1章 羊水の海で」を要約で。今回もトピック3つでまとめました。
【1.胎内環境×脳の発達】
~この10年の間に、
~遺伝学者のほとんどが、いまだに、
~人の脳は生涯を通して体験に敏感に反応するが、
~最新の発見を知れば、
~最新の脳科学は、人間の情緒と自意識が生後一年どころか、
~
~
~
~妊娠中に母親が感じたことや考えたことは、
【2.脳のネットワークと進化論】
~神経細胞(ニューロン)はそれぞれの目的地に到達すると、
~妊娠中期から、ニューロンとそこから突き出た軸索、
~遺伝子は脳の基本的な発達のための設計図を示しはするが、
~この入力情報とは、例えば栄養や健康状態、
~広く受け入れられている考え方によれば、あらゆる種は、
~科学者たちは、生物を、
~どんな生物でも、生存のための行動は二通りである。
~決まっていた発達の道筋が、外の環境に応じて、
生物の場合と同じく、
~こうした知覚は、生まれた後の子どもには、
~不幸な例をあげれば、妊娠中の女性が災害に見舞われて、
細胞生物学者のリプトンはこう述べている。
~「この決定的な重要な"愛か不安か"のシグナルは、
~「
【3.栄養素や薬物、感染症よる影響】
~胎生初期(後期ではない)に飢饉の冬を経験した人は、
~アルコール依存症の母親から生まれた乳児の脳波を見ると、
~タバコに含まれるニコチンが脳細胞の成長を阻み、
~
~最近になって、発育遅延や学習障害、
~妊娠中の麻疹が子どもの精神遅滞や脳性麻痺、
●コメント
まず断りを入れておかないといけないのが、本書の原書「Pre-
つまり、「最近の」とか「最新の」「ここ10年の」
本書では、脳科学的にはフロイトやピアジェの発達論は間違ってい
小見出しに【胎内環境×脳の発達】と書かせてもらいましたが、
また、
~遺伝子は脳の基本的な発達のための設計図を示しはするが、
という「環境×遺伝子」的な考え方は「エピジェネティクス」
考えてみれば、
なので、
~脳のスキャンの画像を見れば、言語、音楽、
は、比較的すんなり受け入れられますし、胎生後、
でも、
~母親の不安やストレスが、
の「人格、性格」
つまり「生物ー心理ー社会」の心理面(サイコ)が→
加えて、
【第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか】
では「遺伝と環境だけで人格をじゅうぶんに説明できないときは、
具体的には、きょうだいの中での役割、
それと個人的に思うのは、母親視点に立つと、
これは母親の「社会×心理」の要因が、胎児の「胎内環境×
もちろん、遺伝子的な要因として、
・「ドーパミンD4遺伝子の多型」
衝動的で飽きっぽい傾向ADHDのリスク遺伝子として裏付けが進
・「セロトニン・トランスポーターの多型」
という面もあるようですが、
ちなみに人種や地域差で言うと、
つまり、
最後に、
LSWに絡めると、
というのは、成長を促す行動(例:
そして、本書の副題が「子どもにトラウマを与えない妊娠期・
すると、時間志向性の傾向や、
資質っていうのはすごくシンプルに考えると「安心体験」と「
そして、その体験の総量は出生後だけでなく、
やっぱり、過去ー現在ー未来が繋がりにくい、
まぁ、本当に悩むケースは、そもそも妊娠期~
伝え方やプロセスによる差はもちろんありますが、
だからLSWが無意味ということではなく、
この辺りがLSWに即効的な効果を求めたり、
ではでは。
【第41回】初期記憶のミステリー
メンバーの皆さま
こんばんは。管理人です。
実は私、今年度から乳児院に関する事業を担当してまして、現在、
それが脳科学、生物学、アタッチメント、発達障害、
と言う理屈を付けて、「バイオサイコソーシャルアプローチ」
まず取り上げるのは「胎児は見ている」で有名なトマス・
こんばんは。管理人です。
実は私、今年度から乳児院に関する事業を担当してまして、現在、
それが脳科学、生物学、アタッチメント、発達障害、
と言う理屈を付けて、「バイオサイコソーシャルアプローチ」
まず取り上げるのは「胎児は見ている」で有名なトマス・
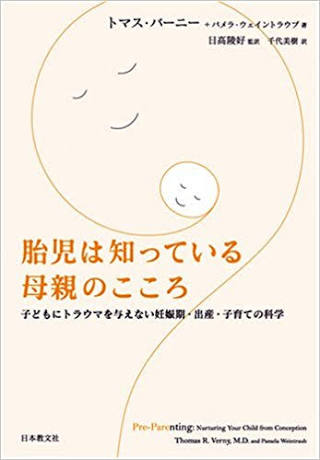
●目次
第1章 羊水の海で
第2章 胎児の意識の始まり
第3章 母親のストレスと胎児のこころ
第4章 子宮は学びの場
第5章 出生体験は性格の形成にどう影響するか
第6章 新生児の感覚と神経はこうして発達する
第7章 「親密さ」という魔法
第8章 経験が脳をつくる
第9章 初期記憶のミステリー
第10章 他人に子どもを預けるとき
第11章 間違いが起こるとき
第12章 子どもの「善意」の基盤をつくる
第13章 意識的な子育て
●内容
全部の章を一つ一つ取り上げるつもりはありませんが、
ちなみに学術的なところを超要約して3つのトピック(
【1.記憶の起源】
~記憶とは何か。そして、それはいつ始まるのか。
~長いあいだ、人の記憶ーそれまで-
~どこまでさかのぼることが出来るのかは個人差があるが、
~多くの人が、記憶は不思議にも3、
~はじめは卵子と精子が合わさって一つの細胞となり、
~細胞か記憶するなんてどうも信じられないという人は、
~過去の研究から、免疫系の働きは潜在意識レベル(
~ホールはまず、被験者に覚醒した状態でのリラクセーション、
~脳と免疫系は双方向の経路を介して、
~心に蓄積された記憶の反映である情緒が、
~この理論はその後さらに発展した。現在では、体験し、記憶し、
~シュミット(1984)は、"情報物質"という言葉を用いて、
~リガンドが全身に流れるメカニズムは、
~つまり、神経科学の最新の発見からいえば、本当の知性と記憶、
【2.顕在記憶と潜在記憶】
~子どもは、まだ未熟な脳でさえできていない時でも、
~記憶を専門にすると心理学者たちは、
~顕在記憶とは、
~それ以外の記憶が潜在記憶である。
~無意識から意識への移行、つまり、
~こうした記憶が増していくにつれ、胎児は潜在的に、
~事実、多くの研究によって、
【3.出生の記憶】
~子宮にいたころの記憶を自然に思い出すことは稀だが、
~おそらくもっとも説得力があり、記録の数も多いのは、
~では、こうした記憶はなぜ、
~まず一つには、出生前と母乳を与えられているきかんは、
~私たちが出生前と周産期の記憶を失っているのは、
~もう一つの要因は、ストレスホルモンのコルチゾールである。
●コメント
まず「オキシトシン」は別名「愛情ホルモン」
他章で詳しく説明がありますが、
いかに乳幼児期に特定の人との日常的にスキンシップや情緒交流を
まさに「痛いの痛いの飛んでいけ~」が効くのは、
NHKスペシャル「ニッポンの家族が非常事態 第二集 妻が夫にキレる本当のワケ」(2017.06.11放送)
http://www6.nhk.or.jp/special/
オキシトシンは環境に左右されるので、
しかし、そのオキシトシンが高濃度になると、
しかし、そのオキシトシンが高濃度になると、
以前、
忘れられると言うのはある意味幸せ、と言うのもよく分かります。なので、本書では例え未熟児であってもNICU(集中治療室)に入り、母子で相互やり取りする機会が喪失することでの、細胞レベルの記憶や脳の発達への悪影響が生涯に及ぼすリスクについて、とても書かれています。
あと、
~脳と免疫系は双方向の経路を介して、
は体験的に非常に心当たりがあります。実は児相に来てから2~
きっと、脳が「こんなストレス無理、休め!」
つまり、今まさに当時のことを「生物ー心理ー社会」
忘れられると言うのはある意味幸せ、と言うのもよく分かります。なので、本書では例え未熟児であってもNICU(集中治療室)に入り、母子で相互やり取りする機会が喪失することでの、細胞レベルの記憶や脳の発達への悪影響が生涯に及ぼすリスクについて、とても書かれています。
あと、
~脳と免疫系は双方向の経路を介して、
は体験的に非常に心当たりがあります。実は児相に来てから2~
きっと、脳が「こんなストレス無理、休め!」
つまり、今まさに当時のことを「生物ー心理ー社会」
知識(認知)
/ \
体験(感覚) - 感情(気持ち)
知識としてだけでなく、
~これからの時代は、脳と心を、
とあるように、今まで色んな角度から触れてきた「
無意識というと根も葉もない魔術的な怪しい印象も受ける人も正直
「肌が合う」「鼻につく」という言葉は昔からあって、
となると、LSWに限らず、
なかなか奥が深いです。その辺りのメカニズムに繋がる話題が、
ではでは。